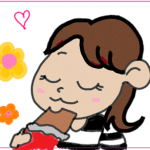親がいくら気を付けていても、赤ちゃんに上の子(兄弟)がいる場合、小さなおもちゃが沢山あって、赤ちゃんが飲み込んでしまう(誤飲(ごいん)してしまう)事故は、世の中にたくさんあるようです。
事故は未然に防いだとしても、ひやりとした経験のある親は多いのではないでしょうか?(←私を含めて💦)
今回、わが家の上の子に「誤飲の危険性」を考える絵本を見つけて読んだので、紹介します。
【絵本紹介】誤飲する「おさるのジョージ」の話
タイトル:『ひとまねこざる びょういんへいく 』
絵本のあらすじ
おさるのジョージがパズルピースをキャンディーだと間違えて口に入れ、いつの間にか飲み込んだために、お腹が痛くなり病院にいって・・・。毎度おなじみドタバタ騒動が起こります!
「ひとまねこざる」は、現在NHK教育番組で放送中の『おさるのジョージ』のこと。
最初は、日本語訳した方が違うのですが、原作者は同じです。
日本でも有名ですよね。
とても好奇心旺盛なおさるなので、なにかしら考えて思ったことをすぐに実行します。それが、とても素敵なアイディアの時もありますが、ちょっと良くない事だったり、危ないことだったりすることも…。そして、その行動がきっかけでトラブルにつながることもあれば、結果的に喜ばれることもあります。
今回ジョージが飲み込んだのは、パズルのピース。
飲み込んでしまって腹痛になります。
誤飲事故は、喉などに詰まってしまうこともありますし、下手したら死んでしまいます。
今回、ジョージは腹痛で済み、無事に出てきたから良かったものの、親としては怖いですよね…。
後半は、ジョージお馴染みのドタバタ劇です(笑)。
上の子に「誤飲の絵本」を読んでみた
私も、末っ子が自分で動き出した(ハイハイ)ので、上の小1と4歳の子どもに「手に届くところに小さなものを置かないで」という話(注意?)を毎日しているのですが、先日この本もあわせて読みました。
二人ともまっすぐに絵をみて聞いてくれました(^^)。
読み終わってしばらく読後感に浸ったあと、「うちだったら、赤ちゃん(弟)が飲み込みそうなものって何があるかなぁ。」
「やっぱりレゴやシルバニアのパーツは危ないから、手に届かない所に片付けしてくれて助かるよ~!有難うね。」
というような話をして、上の子の協力に対して「有難う」と声掛けしました。
上の二人の子ども達もまだまだ「子ども」です。
普段、私から危険性の話は聞いているものの、絵本で読むとやっぱり想像がしやすいように思います。
赤ちゃんが誤飲事故の原因(誤飲しやすいもの)は?
厚生労働省が、誤飲事故の原因になるものを公表しています。
・タバコ(約31%)
・医薬・医薬部外品 (約14%)
・おもちゃ (約10%)
トップ3は、「タバコ」「医薬・医薬部外品」「おもちゃ」となっていて、
他にも「金属製品」「プラスチック製品」「硬貨」「洗剤・洗浄剤」「電池及び食料品」「化粧品」などが続くようです。
赤ちゃんの誤飲で特に注意したい時期は、1歳半まで。但し、3歳頃まで注意して!
赤ちゃんや年齢の低い子どもの誤飲に気を付けたい時期があります。
一番気を付けたいのは、ハイハイが始まってから、言葉が分かるようになってくる1歳半頃までの時期ですが、わが子や保育の経験上、2,3歳児も危険です。
子どもの誤飲に特に警戒して注意したい時期(生後6か月から1歳半)
赤ちゃんの場合、ハイハイを始める時期は、手で何かをつまめるようになっていて、つまんだものを口に持っていくので、「誤飲しそうなもの」に注意する必要があります。
1歳を過ぎると、子どもが立って歩けるようになるので、ある程度の高さまで手が届くようになります。そのため、「誤飲すると危ないものを置く場所」の高さも考える必要があります。
また、1歳児は10~20㎝背が伸びる子どもも多い時期で、指先も器用になるため、ダイニングテーブルの端に置くのも危険です。
1歳半ばには、椅子によじ登れるようになる子も増えるので、親や上の子が警戒しないといけない範囲はどんどん広がります。
一方で、2歳前後になると言葉が理解できるようになってくるため、日ごろから危ないもの、口に入れてはいけないものを何度も何度も繰り返し伝えていくことで、口に入れないことも増えていきます。
厚生労働省によると、
例えばタバコに関しては、このうち、「ハイハイ~つかまり立ちをする生後6か月~11か月の間」で50%を超える事故が起こり、17か月までで90%近い事故が起こると報告があります。
17か月まで、ということは、
「1歳半になれば、グンとリスクが減ってくる」ということです。
たった1年、されど1年。「一瞬も目を離さずに子どもをみておく」ことなんて不可能に近いです!
生後6か月~1歳6か月になるまでの間は特に部屋の片づけや、「子どもが手に届かないところ」に危ないものをおくよう気を付けた方がよさそうですね。
子どもの誤飲にまだまだ注意したい時期(1歳半頃~3歳)
1歳半までが「誤飲事故が特に起こりやすい時期」ですが、今回「3歳児頃までは注意が必要」と私が考えるのは、理由があります。
2,3歳頃になると子どもが「ふざけること」が出来るようになってきて「危ないよ」「駄目だよ」と言われたことをわざとしたがる時期に突入するからです。
このあたりは、子どもによる個人差にもよると思いますが、おままごとセット等でも口に入りそうな大きさのものは、あらかじめ除外するなど親が注意をしておく必要があると思っています。
わが子の場合:子どもの成長は嬉しいけれど…
末っ子が生後8か月になり、ハイハイを始めた頃の話。2週間前は、何かに狙いを定めると「わぁ、1メートルくらい進めたね~!」と、のんびり上の子二人と一緒にほほえましくみていたのですが、あれよこれよというまに、今では、ずり這い(お腹を床にくっつけて前に進むハイハイの形。逆に、お尻を挙げてハイハイすることを「高這い」という)なのに、5秒あれば2,3メートルくらい進むようになりました。
こうなると、「ちょっと目を離した隙(数秒)」に、何かを口に入れてしまう、なんていうことが起こるようになってきました。この「何か」が汚いものだった場合も嫌ですが、口に入ってしまうような小さなものだと非常に危険ですよね!
携帯の充電コードなどもコード内に水分(よだれ)が入って発火したり、関電したら危険なので(←ここは想像です💦)、こまめにコンセントから取り外すようにしています。
誤飲事故が起こりやすい発生時間帯は「16時~22時」!
誤飲事故が発生するとき、曜日による差はあまりないそうですが、誤飲事故が発生する可能性が高い時間帯も分かっています。
それは、「16時~22時」という時間帯です。
この時間帯に、半分以上の事故が起こっているようです。夕方頃から夜にかけてということです。
夕方は、パパもママも、仕事帰りだったり、夕食づくりだったり、お風呂や寝かしつけだったり、その他家事だったり、諸々の事情でバタバタする時間帯ですよね。
自分自身を顧みても、子どもから一瞬目が離れたりすることが多い時間だったりします。
これには「なるほど…」と思わず納得しちゃう親も多いのではないでしょうか。
しかも、保育園や幼稚園といった子どもを預ける施設内での事故は少数なので、保育園や幼稚園並みとまではいかなくても、ある程度、危険なものになりうるものを子どもが手に取れないところに置いておく対策をしておきたいですね。
まとめ
赤ちゃんの誤飲事故は、親はもちろんのこと、上の子どもにも暫く協力してもらって防ぎたいですね。
子どもは、ほんの少し「頼られる」ともっと率先してやってくれるようになります。
誤飲の絵本などを読んで、上の子どもができることを話し合ってもいいですし、「有難う」の言葉がけで、家族で赤ちゃんを守っていけるといいなと思います(^^)。

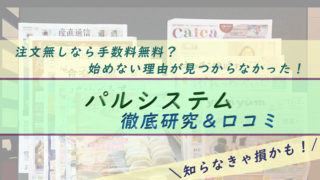

アイキャッチ-320x180.jpg)

.png)


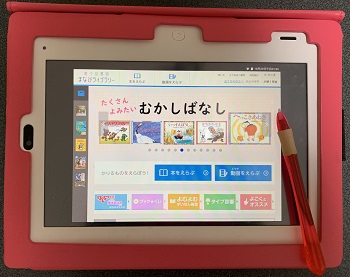
.jpg)
.jpg)